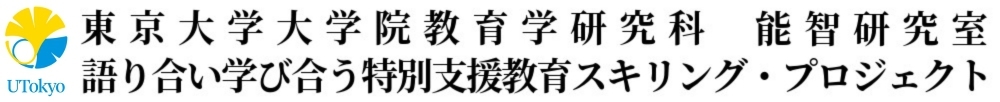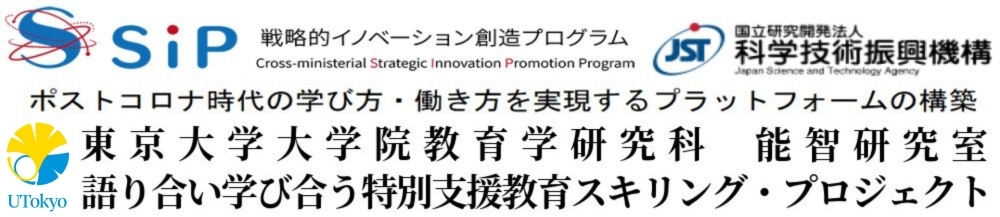能智プロジェクトは2025年4月から、ポスコロSIP山中チーム(室蘭工業大学)と連携し、北海道伊達市の先生方との共働の機会を得ました。山中チームおよび伊達市との連携を記念し、北海道伊達市や伊達市の学校の魅力や能智プロジェクトの活動の様子をご紹介。ナビゲーターは北海道伊達市にお住まいのフリージャーナリスト粟島暁浩さんです。地元目線で語られる能智プロジェクトの魅力もぜひ堪能ください。

第5回 能智プロジェクトが北海道伊達市で本格化(後編)
【伊達を舞台に 教員の働き方から未来を描く】

「伊達の先生の忙しさは全国的な傾向と同様」。7月29日の伊達市教育実践交流・研修会の全体会で、山梨大学大学院総合研究部教育学域の尾見康博教授は、伊達市内の先生の労働環境について調査結果を伝えました。
伊達市の教員の通常週あたりの総労働時間は、平均で54.26時間、最短は10時間、最長は90時間でした。これは、文科省調査の小学校教諭の52.47時間、中学校教諭57.24時間の在校等時間と単純比較はできないものの、同水準とみられます。
全国の1週間あたりの在校等時間の時系列変化では、ここ6年間で全体的な時間は減っていましたが「改善したというところまでは至っていない」といいます。
一般の教員の労働は1日8時間、週5日間の40時間を超えた分を残業とすると、月あたり80時間、週当たりではざっと20時間残業が過労死水準とされています。「伊達でも働きすぎとされる一週間60時間労働は一定程度いる。70時間を超えた人は8%超、80時間超えた人も2%いる」のが実情で、中学の部活の指導者に多いとのこと。
一般的には生徒指導、不登校、いじめ、暴力の対応と、児童生徒の指導の問題でかなり時間を取られているといいます。「逆にいうと、複数の経験をしている人がかなり多い」(尾見教授)とも強調しました。
【悩み抱える教職員多く 伊達市からも待望論】
こうした現状を踏まえ伊達市教育委員会は今回、伊達の教職員に心の健康の維持について理解を深めてもらうことを重視しました。
特に初任者については「右も左もわからず、一番悩みをかかえている頃。中堅の教員は忙しく、話を聞いてもらいたくても気が引けてしまう。一人で悩んでいる先生もいる」とみて、顔見える関係づくりの機会としても期待します。
伊達市の堀井敬太市長も能智教授との対談の中で「悩みを抱えている教職員は多く、教育の現場から『明日からでもやってほしい』という要望があった」と強調していました。
【教員の働き方に着目 新たな学びと働き方の空間創出へ】

能智プロジェクトは、内閣府のSIP事業の取り組みの中で進められています。大きなテーマは「ポストコロナ時代の学び方・働き方を実現するプラットフォームの構築」(通称ポスコロ)。このうち、学びの場で働いている学校の教員の働き方について着目し、新たな学びと働き方の空間の創出という目標に向かって取り組みが進んでいます。
今回のプロジェクトで、能智プロジェクトを支援助言する立場にある、内閣府ポスコロSIP(サブ課題C)のサブプログラムディレクターを務める大山潤爾氏も今回、伊達市を訪れていました。

「空間の創出といっても建物を建てるのではなく、働き方の中では先生と生徒、先生同士、先生とカウンセラーといった、人と人のつながりという場づくりを指す。AIなど新しい技術を入れながら、新しい文化を作りたい。最終的に取り組みが人々の暮らしとか社会にどうつながっていくのかを見つめていく」。人口減少社会にあって、それを元に戻すのは難しいですが「北海道伊達市を舞台に、今を生きる人たちがみんな輝いて、一人ひとりが生き生きと暮らせる社会を目指したい」(大山氏)と、伊達とのプロジェクト連携に大きな期待を寄せています。
堀井市長も「カウンセリングを通して、先生の働き方や子どもたちへの教育の仕方が間違いなく変わる。教育は良くなる方向になっていくはず。先生の働き方が変われば心に余裕ができ、児童生徒へのアプローチも変わり、より学校での生活、児童生徒の学力、生活全般の向上するのではないか」と後押ししていく考えです。
【伊達市でのプロジェクトに手応え だてプロとの連携にも力】

伊達市での研修を終えた能智教授は、伊達市役所で行われた堀井市長との対談の中で「実際に若手の先生とワークを交えた2時間ほどの交流の中で、プロジェクトを非常に高く評価する声をいただいた」と、今後のカウンセリング等の利用に手応えを感じたことを伝えました。
個々の生徒の問題解決には保護者とも連携・協力が大切ですが「決して簡単ではない」といいます。「対応に割く時間にも課題があり、さまざまな問題が絡んでいることに今回改めて気づかせていただいた」。
さらに能智教授は、特別な支援を必要とする児童・生徒への合理的配慮にあたっては、「それだけを切り取って解決するのではうまくいかない」とし、それを支援する環境が必要と説きます。
「大きな要素としてご両親やご家族があり、先生はそことうまく連携しながら、味方につけながら対応することで、より効果的に対処できるでしょう。そのためにも先生を支援する私たちのプロジェクトを利用していただければ」と呼びかけています。

大山氏も「社会は一つの大きなシステムですので、教育という一部分だけでやろうとしても限界がある」とみています。それだけに、伊達市で展開中のSIP事業「だてプロ」との連携や、先行している北近畿エリア(京都府福知山市・与謝郡伊根町)との社会的インパクトに注目した取り組みへの発展も思い描いています。
これらの取組は、室蘭工業大学や福知山公立大学など、それぞれの地元でも親しまれている研究機関を通じて行う予定とのことで、非常に楽しみです(写真は、左から山中真也・室蘭工業大学教授、堀井敬太伊達市長、能智教授、大山氏、心理支援チームサブリーダー青山学院大学教育人間科学部 沖潮満里子・准教授が能智教授を囲んで一致結束を確認したシーン)。
能智教授は「私どものプロジェクトが、やがて全国の方に広がっていくと期待しています。伊達市はそのショーケースであり、その結果として伊達の教育全体の支援につながるよう取り組んでいきたい」と、伊達でのプロジェクト推進への意気込みを語っていました。
(粟島暁浩)