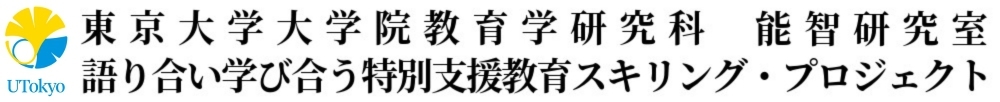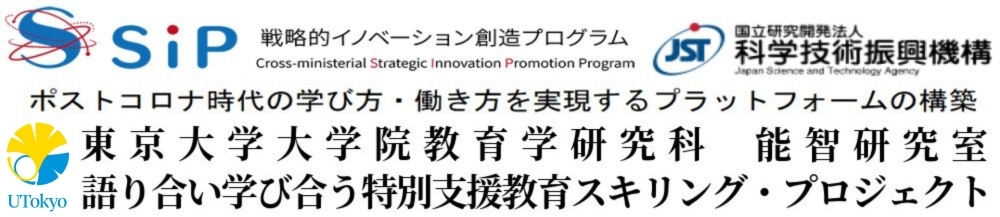シンポジウム
附属心理教育相談室の第20回公開講座が開催されました
2024年12月1日に、東京大学大学院教育学研究科附属心理教育相談室の第20回公開講座「学校における心理支援のこれから:チーム学校の持続的な活動を目指して」が開催されました。
能智プロジェクトは普段、京都府の北近畿エリアを中心に活動をしておりますが、今回は東京圏でのプロジェクト認知向上も視野に入れ、プロジェクト責任者である能智正博教授が所属する附属心理教育相談室の公開講座を共催させていただきました。
はじめに能智教授より、本プロジェクトの紹介も交えながら、公開講座において学校における心理支援を取り上げた背景についてご説明がありました。続いて講座の前半では、学校での心理支援に携わるお二人の先生にご講演をいただきました。
まずお一人目として、石隈 利紀先生 (いしくま・としのり、東京成徳大学応用心理学部特任教授、筑波大学名誉教授)より、『チーム学校におけるスクールカウンセリングのこれから ̶ 児童生徒とのパートナーシップをめざして』と題してご講演をいただきました。(リンクをクリックしていただきますと、配付資料をご覧いただけます)

石隈先生のご講演では、教育現場における課題が現代社会のコミュニティの特徴と密接に関連していることが示されました。その上で、2022年に改定された「生徒指導提要」のポイントを挙げ、チーム学校に関わる当事者としての児童生徒の声を尊重する重要性について解説されました。また、そのような姿勢の実現には、本プロジェクトの名前にも含まれている、“語り合う”という協働作業が欠かせないと強調されました。
お二人目として、綾城 初穂先生(あやしろ・はつほ、駒沢女子大学人間総合学群心理学類准教授)より、 『教師支援のこれから̶ナラティヴ・セラピーに基づく実践事例をもとに』というタイトルでご講演をいただきました。(リンクをクリックしていただきますと、配付資料をご覧いただけます)

綾城先生のご講演では、ナラティヴ・セラピーの基礎的なご説明の後に、先生が学校現場で行われた心理支援の実践をご紹介いただきました。事例では二円法というナラティヴ・セラピーの手法を用いることで、「問題」をめぐる様々な捉え方(ストーリー)が語られ、支援の糸口が見出されていく過程を詳細にご提示いただきました。
後半では、能智教授も加わり、パネルディスカッションが行われました。フロアからいただいたご質問に石隈先生と綾城先生にお答えいただきながら、教育現場において当事者性や多様性を尊重する姿勢をどのように具体的な取り組みに落とし込んでいけるか、組織をどのように変えていけるかといった実践に踏み込んだ議論がなされました。

当日は、学校教育や心理支援に携わる方を中心に約70名の方にご参加いただきました。ご参加くださいました皆様ありがとうございました。引き続き、能智プロジェクトをよろしくお願いいたします。
(おことわり)今回、石隈先生・綾城先生のご厚意で配付資料をアップさせていただきました。資料共有時、原著作者の許可のない改変はご遠慮ください。また、資料の引用元(東大教育学研究科附属心理教育相談室の第20回公開講座用資料)を必ず明示いただけますよう、お願い申し上げます。