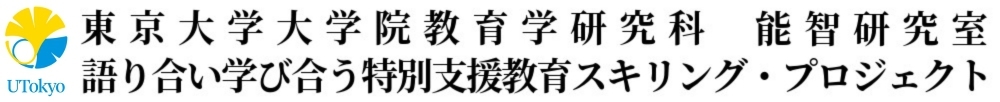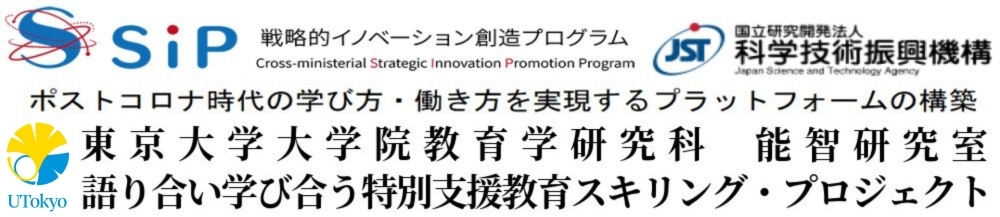福知山市と教育・研究交流連携協力協定の締結に関する、大橋一夫福知山市長メッセージ
東京大学大学院教育学研究科との連携締結にあたってのごあいさつ
福知山市長 大橋一夫
国立大学法人東京大学大学院教育学研究科と福知山市が特別支援教育に関する教員のメンタルヘルス維持とスキル向上へ向けて連携協力協定を締結できましたことに厚く感謝申しあげます。
さて、我が国は少子化により、児童生徒の人数は、本市においても減少傾向にありますが、特別な支援を必要とする児童生徒の数は、年々増加の傾向にあります。
本市は、平成20年度より特別支援教育のグランドモデル地域として、関係部局ヒ連携し、特別支援教育の充実に力を入れてきた経過がございます。
そして、この度の連携協力協定を締結させていただくことにより、福知山公立大学北近畿地域連携機構に「学校組織レジリエンスユニット」が発足し、本市での学校実装を支援していただけることは心強いばかりです。
学校現場では、発達障害など障害のある児童生徒の対応方法が分からず、関係がこじれてしまう教員、自分が築き上げてきた今までの指導方法が通用せず悩んでしまう教員など、教員が直面する精神的な負担は、経験年数だけでは解決できない大きなものがあります。
報道等でも取り上げられているように、精神疾患により休職している教員は、全国で6500人以上となっており、過去最多となっております。精神疾患によリ休職とまではいかなくとも、精神的に負担を抱えている教員はさらに多いものと推察されます。そして、そのような悩みを抱えていても、気軽に相談できなかったり、相談できたとしても、実践に結び付く助言がすぐに得られなかったりすることも多くあるのが現状です。
このような状況の中、今回の連携協力協定によリ、まず「語り合い学び合う特別支援教育スキリング・プロジエク卜」を通して、オンラインにより教員の精神的負担が少しでも軽減できればと考えております。また、特別支援教育のスキルは、今後の学校教育を進めていく上で必要不可欠なものであり、そのスキルの向上は、本市の教育の推進に寄与するものであると確信しておリ、大いに期待しているヒころでございます。
結びにあたリ、今回、「臨床心理学の知見」と「バーチャル空間」を活用した本プロジェクトが、本市において展開されることにより、今後、多様性のある児童生徒の持てる力を伸ばす特別支援教育の充実と、教員の仕事のやりがい・働きがいにつながると共に、さらには、子どもたちや教員のウェルビーイングにつながっていくことを期待しまして、連携締結にあたってのごあいさつといたします。
今後とも、お世話になりますが、よろしくお願いいたします。
 (提携式の様子。左から、廣田康男福知山市教育委員会教育長、大橋一夫福知山市長、勝野正章東京大学大学院教育学研究科長、高橋美保附属心理教育相談室長)
(提携式の様子。左から、廣田康男福知山市教育委員会教育長、大橋一夫福知山市長、勝野正章東京大学大学院教育学研究科長、高橋美保附属心理教育相談室長)